2024.05.20
塾内での確認テスト
こんにちは、進学塾プログレスです。
定期テストに臨む前に
プログレスでは確認テストを行います。
もちろん、事前に範囲を伝え
どのように勉強すれば良いかを
「詳しく」「細かく」指示を出します。
受験学年は『流石』といった結果なのですが
やはり中学1年生や、塾に入りたての子は
「自分ではもっと出来ていると思っていた」
という結果になることが多いです。
言い換えると
『覚えた気になっていた』という感じです。
他には
『勉強時間数の割にイマイチ成績が伸びきらない』
という生徒さんの多くに
インプットは頑張ったものの
アウトプットの練習がまだまだ足りてない
といった印象を受けます。
「もう覚えたからいける!」
という妙な強気は持たずに
実際に自分でテストをしてみて
抜けてしまっている穴が無いかを確認する
最後の作業を怠らないようにしましょう!
カテゴリ:学習について
定期テストに臨む前に
プログレスでは確認テストを行います。
もちろん、事前に範囲を伝え
どのように勉強すれば良いかを
「詳しく」「細かく」指示を出します。
受験学年は『流石』といった結果なのですが
やはり中学1年生や、塾に入りたての子は
「自分ではもっと出来ていると思っていた」
という結果になることが多いです。
言い換えると
『覚えた気になっていた』という感じです。
他には
『勉強時間数の割にイマイチ成績が伸びきらない』
という生徒さんの多くに
インプットは頑張ったものの
アウトプットの練習がまだまだ足りてない
といった印象を受けます。
「もう覚えたからいける!」
という妙な強気は持たずに
実際に自分でテストをしてみて
抜けてしまっている穴が無いかを確認する
最後の作業を怠らないようにしましょう!
2024.05.17
ルールを守るということ
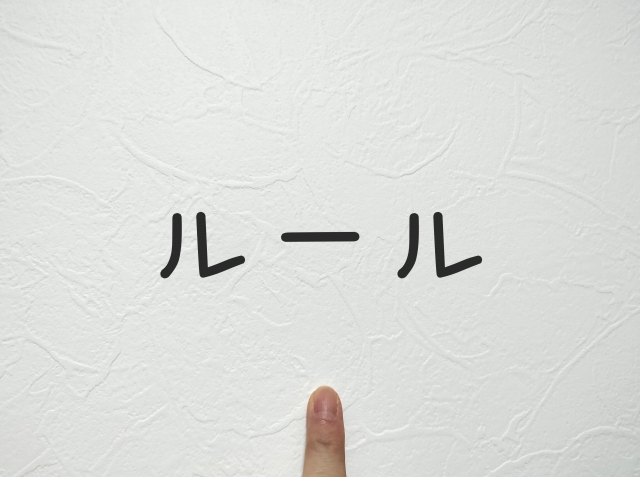
こんにちは、進学塾プログレスです。
社会では、場所ごとに設定されたルールが存在します。
しかし、ごく稀に「ルールにとらわれない人こそが
天才タイプだ」「個性派だ」と勘違いする人がいます。
実はそれは全く正反対のお話です。
ルールをきちんと守る人こそが「頭が良く」「個性的」
な人になれる可能性を秘めています。
ルールを守るということは
ルールを知り尽くしているということ。
言い換えると
そのルールの中にある可能性を最大限に引き出し
工夫を重ねることで次の可能性を生み出す
ということにつながります。
スポーツなどが分かりやすいかもしれません。
たとえばサッカー!
脚のみでボールに触れることが出来て
相手チームのゴールにボールを入れたら得点!
シンプルなルールですが、その枠組みの中で
そしてルールに違反しないという制限内で
現在はあらゆる作戦や手法が研究されています。
これはいわば、研究してきた人たちの
「個性」によるものであり
そして「頭の良さ」の結果だとも言えます。
逆に言ってしまうと
ルールを守らないということは
何も考えていないことと同じです。
可能性を追うことや、個性を追求することを
放棄してしまうことになります。
お話のまとめ。
個性を大事にしたい、頭が良くなりたいのならば
まずはきちんとルールを理解して、守りましょう!
カテゴリ:学習について
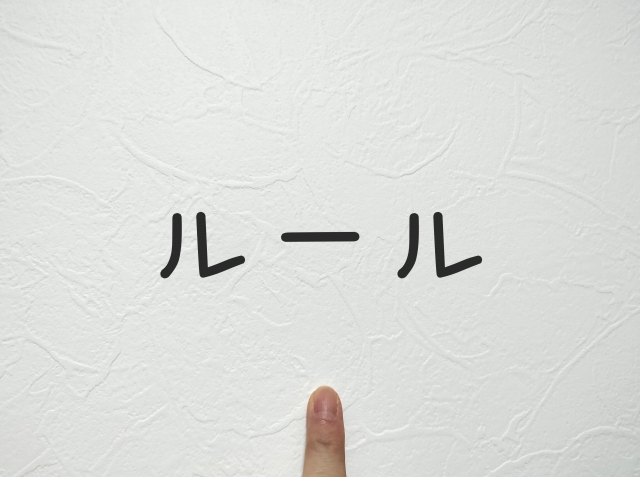
こんにちは、進学塾プログレスです。
社会では、場所ごとに設定されたルールが存在します。
しかし、ごく稀に「ルールにとらわれない人こそが
天才タイプだ」「個性派だ」と勘違いする人がいます。
実はそれは全く正反対のお話です。
ルールをきちんと守る人こそが「頭が良く」「個性的」
な人になれる可能性を秘めています。
ルールを守るということは
ルールを知り尽くしているということ。
言い換えると
そのルールの中にある可能性を最大限に引き出し
工夫を重ねることで次の可能性を生み出す
ということにつながります。
スポーツなどが分かりやすいかもしれません。
たとえばサッカー!
脚のみでボールに触れることが出来て
相手チームのゴールにボールを入れたら得点!
シンプルなルールですが、その枠組みの中で
そしてルールに違反しないという制限内で
現在はあらゆる作戦や手法が研究されています。
これはいわば、研究してきた人たちの
「個性」によるものであり
そして「頭の良さ」の結果だとも言えます。
逆に言ってしまうと
ルールを守らないということは
何も考えていないことと同じです。
可能性を追うことや、個性を追求することを
放棄してしまうことになります。
お話のまとめ。
個性を大事にしたい、頭が良くなりたいのならば
まずはきちんとルールを理解して、守りましょう!
2024.05.15
勉強とは孤独なもの…!

こんにちは、進学塾プログレスです。
塾でテスト前の時期になると
『勉強会』とか『お友達と一緒に勉強している』
というお話を聞くことがあります。
まだ勉強に慣れていない中1や
中2の1学期くらいまでなら
勉強を始めるきっかけとしては良いと思います。
ただ、勉強とは究極のところ
「孤独なもの」です。
学力向上に最も作用する
「自主学習」とは結局のところ
「孤独な戦い」です。
「誰かと問題を出し合う」とか
「知っている人がそばいる」といった
安心感や楽な勉強方法は、特に意味がありません。
「友達が勉強しているから」とか
「周りが集中しているから」といった
理由付けのようなものは一切必要なく
自分に必要だからやるんです!
繰り返し言いますが
『やる気はあるが、行動に移せない』という
段階の人は
一つの手法として
「友達と一緒に始める」とか
「集中出来る場所を利用する」のも良いでしょう。
ですが、その先
高校受験や大学受験というレベルの話になったとき
「さあ勉強するぞ」と意気込んだ時には
間違いなく自分以外の誰かは存在しません。
受験勉強とは、言い換えると
「自主」学習だからです。一人だからです。
つまり、勉強とは孤独なもの。
しかしその孤独に負けずに
『自分の為』に頑張った人が
目標とするものを手にすることが
出来るのです!
頑張りましょう!
カテゴリ:学習について

こんにちは、進学塾プログレスです。
塾でテスト前の時期になると
『勉強会』とか『お友達と一緒に勉強している』
というお話を聞くことがあります。
まだ勉強に慣れていない中1や
中2の1学期くらいまでなら
勉強を始めるきっかけとしては良いと思います。
ただ、勉強とは究極のところ
「孤独なもの」です。
学力向上に最も作用する
「自主学習」とは結局のところ
「孤独な戦い」です。
「誰かと問題を出し合う」とか
「知っている人がそばいる」といった
安心感や楽な勉強方法は、特に意味がありません。
「友達が勉強しているから」とか
「周りが集中しているから」といった
理由付けのようなものは一切必要なく
自分に必要だからやるんです!
繰り返し言いますが
『やる気はあるが、行動に移せない』という
段階の人は
一つの手法として
「友達と一緒に始める」とか
「集中出来る場所を利用する」のも良いでしょう。
ですが、その先
高校受験や大学受験というレベルの話になったとき
「さあ勉強するぞ」と意気込んだ時には
間違いなく自分以外の誰かは存在しません。
受験勉強とは、言い換えると
「自主」学習だからです。一人だからです。
つまり、勉強とは孤独なもの。
しかしその孤独に負けずに
『自分の為』に頑張った人が
目標とするものを手にすることが
出来るのです!
頑張りましょう!

 RSS 2.0
RSS 2.0